県内一の進学校、県内トップクラスに元気に卓球する山東にお邪魔させていただきました。
遊びにというよりも最近見つけた指導法、卓球の理論を実際に試す被験者になってもらおうという趣旨のもとひたすら同じことを一人一人に教え続けた。
メインはフォアバックの基礎打ちを最小単位の運動から教え、面移動を起こさないような動き+下半分に安定して当たるようなスイング+後ろから前に過剰に運動が入らないような制限を核とし、股関節の運動や肩関節の運動、上腕の使い方と前腕始動の考え方を教えていった。
教えるといっても、もう眠くて口が回らなくて、なんなら3時間くらいぶっ続けでフォア打ちなりドライブ対ドライブしてたから頭がボーっとしてて何をいっているかわからなくなることもしばしばだった。。
しかし終わり際に結局何が大事だと思う?と聞くと引き付けること、と皆答えてくれるので教えてよかったなぁと思うところ。
この引き付けることが大事と、ひきつけろひきつけろと洗脳することなく思わすことができただけで大正解かと。
他にもOB勢に肩の使い方を実際に肩を引いて教えてみたら弾く感覚を運動単位で覚えてくれて、突如低弾道のぶち抜き系のドライブが安定しだしたり。
多分一般的な感覚を教えて大きな動きを~という手順だと10分そこらでこれ程にドライブは変わらないんだろうと思う。
実際感覚ベースの指導を極めた三段選手も指導に苦労しているとのことだし、所謂一般的な卓球指導では飲み込みが悪い人は少なからずいる。
そうした選手に「弾く感覚、擦る感覚はあるか」とごくごく一般的な方法でアプローチしてみようかと私もやってみたが、実際全くハマる感じは無かった。
そこで擦る感覚の最小は橈屈運動+上腕~肩にかけての上下方向の運動の最小単位(=上下方向に微動すること)、弾く感覚の最小は肩を最大限に引いて、そこから戻る運動の最小単位(=前後方向に微動すること)と定義し、体の使い方を教えたら、いきなり弾く感覚を覚えて、当て擦りの感覚を理解してくれた。
一般的感覚重視の指導の欠点として、その人に合った弾く・擦る感覚のストックを指導者が無数に持ってなければ即身に付けさせることができないことがあるように思える。
感覚を先に付けるよりかは運動から感覚を定義してあげた方が、その運動を調整することで感覚が変わる為自分で制御しやすいのかもしれない。
とりあえず今日の収獲の一つとして、一切感覚指導が合わないタイプで十分に卓球の勉強をしている選手には運動単位の指導をしてあげると化ける可能性があるということ。
如何せん、最小の運動単位をベースとして、全ての技術に、全ての状況で応用が利く考え方があることまでは説明できなかったが、流石にその辺はブログを読んで考えてもらうしかないかも。。
1コマ50分の対話式講義10コマくらいできるぐらいにネタはある程にシナジーを見つけることはとりとめがないし、何か新しいことに気付いたら他の技術との共通点は無いか常に考えて探し続けて欲しいなというのが正直なところ。
私が常にアンテナを張り巡らせてシナジー指導論を作ろうとしているように、小さな違い、小さな共通点からシナジーを見つけていってほしい。そういう意味ではカテゴライズは重要だね。
また、十分に基礎ができている粘着使いのループが所謂WRM式の遅くて回転量のあるループだったが、流石に打ちこんでないにしてもとりやすかった。
遅いループってそれなりに打法設定がなってないと次にくるボールが打ちづらいし、カウンターもされやすい。対ぐっちぃ試合を見ていてもバチバチ系にはループは効いてないし、知り合いのバチバチ系がプラになってから内容勝ちをしている試合もあったことから、プラで粘着を使ってまでする戦術では無いだろう。
最近の日本選手のループドライブのトレンドを見ていると、中速度で回転量があり低弾道のループがプラになってから流行っている。
球筋はキレイだが下がらないとカウンターすることが出来ず繋ぐことしかできず、次のボールは返しやすいため狙いやすいというストーリー。
粘着系の打法とも言われる「ヘッドを軽く起こして横から引っ張る」打法を、基礎出来てるし基礎すっ飛ばして実演しつつ教えてみたら、すんなり習得してくれた。
上手に打てる人でもヘッドを下げて下から上にもっこり弧線を描くループがベストと盲信する人は未だに多い。
勿論完璧に決まれば強いループだが、プラ時代でかつプラの品質もあがってきた現在、そうしたループでイレギュラーを期待することは難しいし浮いてしまうことの方が多い。
実際そうしたループがプロ間で流行っていないことからしても、攻撃完遂性能も高くはないという証明になる。
それでいても「遅くて高いループは効く」という人はいるが、そもそもその効くループの品質がどの層のどの戦型でどういう待ちをしているかで大きく異なる。
後ろから前のスイングを多く入れてしまうタイプなら効くだろうし、現代的な寄せ方を知っているタイプには効かないだろう。
「とりあえず遅くてかかっているループ」は自分なり周りを見て考えて使う必要がある。
またループ使いはバウンド後の弾道を考えることは必須となる。
バウンド後に低い弧線になるのか、それとも弾んでしまうのか、調整することが出来なければあくまでチャンスボールのなるリスクが付きまとう。
流石にここまでは教えてはいないが、多分上手い人のボールの出し方を知ったら今後もそっちに寄ってくれることかと思う。
以上外部に指導をしに行って感じた事でした。
1対1で経験者かつ運動が人並みにできるタイプであれば最低10分、最高でも1時間あれば連打と引き合い、前陣フォアフォアまでは習得できるみたい。
それもこれも基礎打ち設定を変えただけで、となると最近の研究テーマはなかなかに効率があるものなのかも。
元気であれば中学生にも教えに行きたかったが、もう足が限界で教えることはできませんし、きちんとしたコーチがついていてあまり口出ししづらい環境だと私なんかが何を教えても「嘘だー」と言われてしまいそうだし残念なところ。
今回は知り合いの三段選手、それも共に技術研究と指導しあう関係にあったからこそなせたこと。
柔軟な思考、広い打法・技術・練習に関する知識を有し、常に進化し続ける彼の元で卓球ができる山東は間違いなく素晴らしい環境。
センスがある子も多くいたし、まだまだ上手くなる。
応援しています!!
ということで、三時間強も運動したのに体重が減っていないのはどういうことでしょう。。
内臓脂肪いっぱい燃やした気でいたんですけどね。
とりあえず今日は29(にく)の日、肉増量のすた丼を食べにいきましょうかね!
・・・また太るなぁ

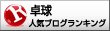
コメント